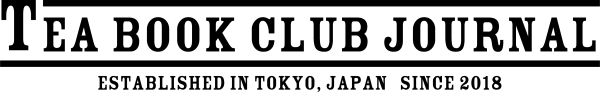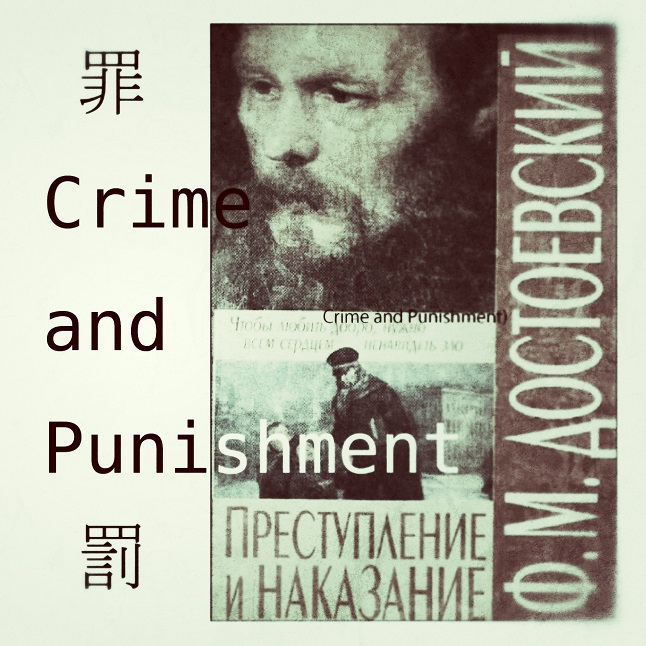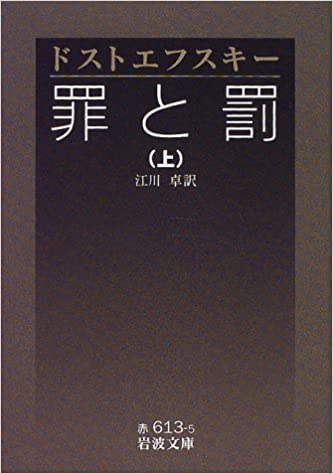紅茶と読書会 第一回報告
課題本 「罪と罰」 フョードル・ドストエフスキー著
1866年 発行
~1860年代半ば 酷暑に見舞われたサンクトペテルブルクの7月~
勢力拡大の一途をたどる西欧諸国に対し、社会主義が台頭しつつあるロシア。
優秀であった元学生ラスコリーニコフは、貧困から金貸しの老婆に対する強盗殺人を企てる。
自身の思想的正当性を確信していたはずの彼は、思いがけない殺人を起こしてしまった事から精神の均衡を保てなって行く・・・。
はたして彼の罪は、そして罰とは何であるか、救いは生まれるのか。
おそらく日本で最も名の知られたドストエフスキー作品。------------------------------------
以下内容に触れる箇所もございますので予めご了承下さい。
紅茶と読書会、第一回として「罪と罰」を課題本とする会を開催いたしました。
本を読まない人でも知っているであろうこの小説、しかも上・中・下と3巻にわたる長編。
読むのにもかなり時間と労力がかかるという事で開催2か月ほど前から告知をしていました。
課題図書に選んだ理由としては「ドストエフスキーを読んだと言いたい」と言いたいが為です。
参加者の方達の中にもそういった動機があった方がいたのかどうか、それは定かではありません。
一つだけ分かった事は、読むのが大変な小説は読書会も大変だと言うことです・・。
あらすじ 登場人物、意見、考察など
この小説のあらすじはあまりにも有名でしょう。
たいていは「貧乏な若者が金貸しの老婆から金を奪うために殺人を犯すが、罪の意識と後悔の念に囚われ、最終的には自首をする」
と言ったところでしょうか。
これだけ聞くとなんてことないヒューマニズム小説にしか思えませんが、やはり腰を据えて読むとその内容の重厚さ、普遍性は心にしみるものが有りました。
特に私が感じたのは「人間」の事が非常によく書けているな、と言う事です。
しかしこの小説を読まんとする者の心をくじいてきた原因の一つに、ロシア人の姓名が長いうえに、一人が複数の名前で表される点があると思います。
何度も登場人物の一覧を確認しないと訳が分からなくなってきます。
途中で名前と人物を取り違えようものなら、もう悲劇ですね。
--------------------------------------
【上】
この小説の主人公は青年ラスコリーニコフ(愛称ロージャ)、論文を発表したこともある秀才ですが金銭的な問題で大学を辞めざるをえず、鬱屈とした日々を過ごしています。
小説の序盤から中盤ころまではこの24歳の若者の殺人計画(序盤では明かされない)と心の中の混乱を独白で読まされるので中々辛いです。上を読むのが一番辛かった、と言う意見も多く見受けられました。
しかも行動、言動に意味不明な部分も多々あり、分裂病なんじゃないかとすら読書は思ってしまいます。
しかし彼が殺人を犯してからの人間描写が本当リアルです。人を殺す、と言う行為を平常心で行う事の出来る人間も中にはいるのでしょうが、大多数の人間は彼と同じような精神状態に陥るでしょう。
金品強盗を企てていたのにもかかわらず、殺した直後に金品を奪う目的すら失念してしまう、つまり殺人犯した事の衝撃は自分が想定していたものをはるかに上回るものであり、目的を遂げた直後から激しい後悔の念に苛まれてしまいます。
ラスコリーニコフは少しの金品しか持ち帰れず、家に帰るとそれを見るのも嫌になってしまい、よその家の裏庭に埋めに行きます。
計画実行の当日の描写はサスペンス要素も多くあり、ドキドキしながら読むはずです。
多くの人が「罪と罰」に対して構えて臨んだと思いますが、話が面白い、と言う意見が参加者全員から上がりました。やはりいくら純文学的な、人間の心や魂の揺れ動きを表現したくとも、こういった箇所のような小説として話が面白い、と言う前提がないと名作になりえないのかなと、感じます。
ラスコリーニコフは事件後に別件で警察から呼ばれ出向いた際「今までとは全く変わってしまったのだ」と言う強い感覚、すなわち「断絶感」を味わいます。この感覚は個人的に非常に共感できました。
何か「悪い事」や「後ろめたい事」をした人が共通に味わう感覚なのでしょう。事の大小はあれ。
彼は自分のしでかした事の苦しみに耐えられず、川に身を投げようと町を彷徨い歩きますが、その時に「生きていたい!」と強く思います。
結局ラスコリーニコフの苦しみは死にたくないと言う思いから生じる訳です。
辛いから死にたい、でも生きていたい、だから苦しい。
ここで大切なのは殺された老婆とリザヴェーダの存在だと思います。
いくらラスコリーニコフが苦しんだところで、彼はこの二人を殺しているのですから。
しかし事件直後に気を失って4日も昏睡状態に陥り、明らかに挙動不審さが増しているのにもかかわらず、病気で可哀そうに、という事で付き合ってあげている周りの人達がすごい、と皆の意見一致していました。普通疑うだろ、と突っ込むべき箇所です。
————————————–
【中】
物語が中盤にさしかかると家族が上京したり、妹の婚約者ルージンとひと悶着起こしたり、
刑事コロンボさながら、何でもお見通しのポルフィーリィが登場したりと新たな展開が生まれ、そうした中で落ちぶれた元役人マルメラードフの娘であり心清らかな娼婦、ソーニャとの交流が生まれます。
この中に入ってから話が面白くなってきたという意見が多かったですね。
「やばい人しか出てこない」
「あえて娼婦を選ぶ不幸フェチ」
などなど。
社会主義的なものに対する批判なども中のp136あたりに見られます。
彼が殺人を犯した本当の理由は中々明らかされませんが、ポルフィーリがラスコリーニコフの論文に関して追及する箇所では功利主義=非凡な者は何をしても許される、と言う事への問題提起とも読めます。
そしてラスコリーニコフがそれを肯定しているのではないかと。ポルフィーリィが徐々に追い詰めていく感じがたまりません。神は全て知っている、と言うような役割を与えられているのだろうと感じながら読んでいました。
中巻の後半ではついにラスはソーニャに自分が老婆とリザヴェータを殺したと示唆します。
そしてその話をズヴィドリガイロフが壁の向こうで聞いている、と言う場面はまるで映画のワンシーンのようで面白いという意見があがりました。
このズウィドリガイロフ、傍から見るととんでもないクズ野郎です。
ラスの妹ドゥーニャを家庭教師にして関係を迫ったり、奥さんを殺したり(恐らく)、少女を凌辱するなど、書かれていないだけで、もっと酷い事をして来たと思えてしまう好色漢です。
しかしこの男、前半ではひどい人間としてのみ描かれていますが、下巻の第六部六~七の60ページ程では主人公とも呼べるような、さらにカッコよさすら感じてしまう男として登場します。
-------------------------------------
【下】
下の序盤はルージンが策略を図りソーニャを陥れようとしますが、ルージンの友人であったレジャベートニコフの助けもありルージンをコテンパンにやり込めます。
やはり地頭がいいラスコリーニコフ、たまに物凄い出来るやつに豹変し、弁も立つので頼もしいくらいです。
この流れも読者を飽きさせないための場面なのかと個人的に思いました。
この後ラスコリーニコフはソーニャに殺人を告白、またなぜ殺したのか、その理由についてようやく述べます。ナポレオンの偉業と老婆殺しを同列に並べ、自分が偉大な人間になる踏み台として殺人を行ったと。
言うなれば「思い切ってやるものが権力を持つ」その為に殺した、と言えますでしょうか。
ここには現代にも通ずる人間社会の縮図が垣間見えたような気がしました。
政治家や起業家なども「思い切ってやった」結果富と権力を得る、その他大勢は「やった人間」に従うのみ。いくら政治や資本家に文句を言ったところで「やってない」人間は力を持てず何も変えられない、と言う示唆であると。
ナポレオンを例に出しているのでやはり戦争の事も含まれているのでしょうか。
しかしラスコリーニコフはナポレオンではなかったと自覚していることを吐露し、また今までの分裂症はなんだったんだというほど明瞭な自己分析を始めます。
何故ラスコリーニコフはソーニャに告白しようと思ったのか。
参加者からは
「ソーニャは信仰の対象、教祖のような存在」
と言う意見が出ました。
確かにラスコリーニコフは最後までキリスト教を信じようとしませんでしたが、教えではなくソーニャに対しては信仰と呼べる感覚を持ったのかもしれません。
ソーニャのどこへでもついて行く、と言う下りはラブストーリーとしても成立していますね。
そして、ズヴィドリガイロフです。
ラスコリーニコフの殺人をネタにドゥーニャをどうにかしようと迫りますが、拳銃で反撃にあい、さらにどんなに強く願ってもドゥーニャの愛を得る事が出来ないことを悟るのです。
この男はクズですが、実は頭は悪くなく、思想や語りなどにも深い部分が感じられます。
しかしこの男の人生を貫くものとして「圧倒的な虚無」があるのではないでしょうか。
いくら女性と関係しようが、金が有ろうが彼の心は満たされるものは無かったのでは、と個人的に思いました。
ドゥーニャの拒絶によりその虚無をまざまざと眼前につきつけられ、もはや生きている意味がないと感じ、残ったお金をソーニャの妹たちの為に使い、美しい悪夢を見ます。
そして「アメリカに行ったと言っておいてくれ」と街角に立つ兵士に言い残し、自らのこめかみを拳銃で撃ち抜くのです
。
当時のアメリカは「新世界」と言う言葉で認識され、死後の世界=新世界=アメリカ、そしてアメリカに旅立ったズヴィドリ氏。
ここの下りは皆さん印象的だったようで、むしろかっこいいと言うような評価につながったのでしょうか。虚無感と言う点で共通するものを北野映画のラストに感じます。
--------------------------------------
【エピローグ】
下の最後でラスコリーニコフは広場の十字路に口づけをした後、自首をします。
周囲の人々の尽力もあり懲役わずか8年と言う短い刑期で済みますが、母親はこの事実に気を病み現実を受け入れられないまま亡くなってしまいます。
シベリアに送られながらも、ソーニャに見守られながら刑期を過ごす中で、病気になってしまったと描写を読んだときはラスコリーニコフの死を覚悟しましたが、ソーニャの見舞いの結果無事回復します。しかしその後なんとソーニャが病気になるというラノベ並みの急展開に、これまた死を覚悟しますがすぐによくなります(ホッ)。
やや本筋とは外れますが、p396~「全世界にはびこる疫病」と言う描写、これは現代社会を予見している、とも思えますが当時からそのような世の中だったのか、つまり人類にとって「良い時代」と言うのはどこにもなかったのか、未来はさらにひどくなるのか・・・。
皆さんどう思ったでしょうか。
この二人の病気の後、断絶とは真逆の感情、意識外に芽生えた愛と言う感情がラスコリーニコフに生まれます。手をお互い差し伸べてロージャが膝に覆いかぶさる場面は感動的で、未来への明るい希望も示唆されたラストには、思わずカタルシスを感じずにはいられませんでした。
--------------------------------------
かなり長い小説のうえに難解な箇所も多いですが、読んで損は無いと思いますのでドスト未読の方にも是非お薦め致します。