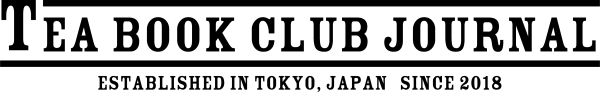第23回 紅茶と文学 報告
課題本 「一人称単数」
村上春樹著
2020/10/4@吉祥寺
2020年 発行
■ハルキストではないのですが
今回の課題本は2020年に刊行された「一人称単数」でした。
新刊を選ぶことはめったに無い、と言うか初めてですね。
中国行のスロウボート、かえるくんから始まり、翻訳ものを入れると4回目の村上春樹関連という事になります。
どんだけ好きなんだ!と思われそうですが、別にハルキストのつもりは全くないんですよね。スパゲッティを毎日ゆでませんし、ジャズやウイスキーついてうんちくを語った事など一度も無いのです。
好きであるのは間違いないですが、超絶熱狂的と言う訳ではありません。
なので村上春樹?どうなの?と思っている方も逃げずに最後までお読みいただけると幸いです。
以下内容に触れる箇所もございますのでご了承ください。
-ご挨拶-
今回は9名の方にお集まり頂き、初参加の方が2名でした。
今回の紅茶
- 水出しアイスティー (ニルギリ) FOP+ルフナ
今回は全く味の感想が聞こえて来ませんでした!泣
- 水出しアイスティー (ニルギリ) FOP+ルフナ
■池袋→吉祥寺へ会場を移動
7月に開催して以来約2か月振りの読書会となりました。
当読書会はもともと池袋で行っていたのですが、コロナで会場が使えなくなってしまい、どうせやるなら近所の方が楽と言う理由で、今後は吉祥寺近辺での開催が基本となりそうです。
ハモニカ横丁も閑散としていてよるとまったく雰囲気が違うんですね。
朝のハモニカ横丁。
開店前のブックマンション
■短編集は今も面白い
あれだけハルキストではないと言っておきながら、主催者は村上春樹は長編から短編まで、エッセイ類を覗いて小説はほぼ読んでいます。
中には内容やタイトルを忘れてしまっているものも多いですが、おそらく全作家の中で一番読んでいる人になりますね。
最近の長編はあまり趣味ではなく、80~90年代の作品を好みます。お気に入りランキングをあげるとすると
1位「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」
2位「羊をめぐる冒険」
3位「国境の南、太陽の西」
ですかね~。最近の長編はそうでもないですが、短編はまだまだ面白いと思ったので今回も課題本にした次第です。
■春樹風読書感想文!
今回は収録作品から一つ選んでいただき、村上春樹風に感想文を書いて頂く、と言う試みをしました。
やや無茶振りでしたが皆さん力作を仕上げてくださいました。ありがとうございます!
以下掲載しますが、結構長いです。多少加筆修正がしてあります。
(↓主催者は当日のお土産紅茶パッケージに、ティーバッグの悲哀について春樹風に作文)
「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」 D
もうずいぶん前の話になるが、当時僕はある一人の女の子がそれなりに好きだった。
その子と渋谷で会った時のことを話そうと思う。
(それなりにと言うのは、僕らはまだ出会ってまもなく、人柄がお互いよく分かっていなかったのだ。ただその瞳の形が僕の好みだったという事だ。)
-その女の子と出会う前に、僕は渋谷の東急ハンズ裏にあるバーを見つけていた。
ある日外付けの白い階段を上り、窓から店内を覗くとバーテンダーがカウンターに座り、一人本を読んでいて、店内には心地よい音楽が聞こえていた。
干渉されずゆっくりと過ごせる様な気がして―そしてその予感は見事に当たっていた。
心地よい根額はボサノヴァと呼ばれるジャンルで、ブラジルのハーブから作られたお酒がいくつも置いてあった。
店名はブラジルの言葉で「船」と言った。-
「少し珍しいお酒を飲みにいかない?」
僕は女の子に言った。
その子と酔い引き連れて坂を上ると、変わらずにそのお店はあった。
2階から静かにボサノヴァが漏れ聞こえていた。
僕らは思っていたよりも急な階段に苦労しながら昇り、店内に入ると見覚えのあるバーテンダーが静かに出迎えてくれた。
僕らは並んでカウンターに座り、目当てのものを注文しようとした。
「ブラジルのお酒ありましたよね?飲みやすいものをロックで二つ」
僕がそう注文するとバーテンダーは戸惑い見せた。まるで目の前にいる僕の言葉がわからないようだった。顔は日本人なのにイタリア語を話されたような、そんな場面に出会したような顔だった。
「ブラジルのお酒ですか?当店にはありませんね…」
「え?」
「当店はお酒はスコッチがメインです。スピリッツならある程度ありますが」
「たしかに僕は以前ここでブラジルの蒸留酒、ハーブを使ったような、そんなお酒を飲んだことがあるんですが」
「いや、当店でそのような、ブラジルのお酒を扱ったことはありません」
信じられなかった。僕の記憶の中では鮮明に、ここで、このバーテンダーから、ボサノヴァを聴きながら、少し辛く少し薬のようなつんとした匂いのする味の印象が強く残るお酒を飲んだのだから。
隣の女の子が怪訝そうな顔をするが、もはやどうでも良かった。
僕の記憶の中にあるお酒が出てこない、この状況がとても受け入れ難かった。
しかし、こうもはっきり言われた手前、何も言えなかった。僕は釈然としないまま、何かしらのウイスキーを頼み―多分グレンリベットとか何かを―穏やかに飲み、そのバーを後にした。
そして、その女の子とはそれきりになった。
あのお酒は確かにあったと今でも思う。あの味のことを強烈に覚えている。
でも、もう味わえる術を僕は知らないのだ。
「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」 W
「狐につままれたかと思ったわ。私は動物アレルギ-だからくしゃみが出そうだった」
彼女はそこまで言って手元のギムレットを飲み干した。
ぼくはナッツをかじりながら彼女-どこにでもいそうな、でも探している間は絶対見つけられない、そこにいるのに気付けないような女性-の横顔を見た。
「絶対にありもしないCDなのに店頭にあったなんて」
いつもより混乱しているのはその早口でわかった。
「こういう事があるとね、期待しちゃうのよ私。もっともね私が頭の中で思い描いたもの、例えばもういなくなったミュ-ジシャンや作家の新作とかね。そういうものに出会えるんじゃないか、とか」
彼女の言いたいことは、今の僕にはわかるようでわからない。つまり、頭の中をゆっくる素通りしていただけだった。
僕の前の前には壮大な能楽堂があって、過去の麻衣氏が若い舞手の夢の中に現れ古の舞を教えていた。とてもロマンあふれる夢だ。つまりこういう事なのだろう。
彼女はまだしゃべり続けていた。
僕はパスタをゆでながら-いや正確にはゆでてはいない。ここは地下のバ-なんだから脳内で想像していた、と言うのが正しい-退屈な気持ちになった。
こういう事はよくあるのかもしれない、そういう話だった。
「ヤクルト・スワローズ詩集」 S
最初にお断りしておきたいのだが、私は野球というものにまともな関心を払ったことがない。
もちろん、月並みに有名な選手は知っているし、幼い頃は父に連れられて何度も球場に足を運んだ。いつの試合かは忘れたが、幸運にもホームランボールを手にしたことだってある。
それでも、どういうわけか野球にはこれといって夢中になれなかった。初めてチャーリー・パーカーを聴いた時に感じたような、戦慄が体中に駆け巡るような感覚は、残念ながら野球という競技からはただの一度たりとも起こらなかった。
そんなわけで、私がヤクルト・スワローズについて語ることなどついぞ考えもなかったし、そもそも日本中の野球ファンを探したってそんなことをする人はまずいないだろう。
「ヤクルト・スワローズ」という存在は、つまるところそういうチームなのだ。チームは一応この世に存在している、それ以上でもそれ以下でもない。
・・・・・・・・・・・・
そんなチームについてわざわざ語ろうとすることに、何の意味があるだろうか?
そんな冴えないチームの試合に足しげく通っては、黒ビールを片手に選手のお尻について詩をしたためるような人間がいるだって?そんなバカバカしい冗談を一体誰が思いつくだろう。
それはまるで「バードは一度でもボサノヴァを演奏しようと思っただろうか?」という問いに匹敵するほど、もはや宇宙規模の謎だ。
でも、正直そんなことは私にとって全くといっていいほどどうでもいいし、わざわざこの場を借りて言及するまでもない。
寂寥感が漂う秋の夜風のように、チームはきっと今日も負け戦に終わるのだから。
「石のまくらに」 N
今まで避けてきた村上作品を読んでみた―しばしばとまではいかないが、手に取る機会はあったにせよ。短歌が出てくる話が好きかもしれない。
一人称単数で繰り広げられる世界はとても興味深いものばかりであった。しかし同時に春樹風に文書を書くと言う行為の限界を感じざるを得ない。
「クリ-ム」 H
「その老人は幻想だったのではないかしら」
「完璧な幻想など存在しなんだよ。完璧な絶望が存在しないように」
「確かに幻想の中には真実が含まれているし、現実の中に思い込みや希望が入っていることもあるかもしれない。少なくとも「クレム・ド・クラム」と言う考え方は素敵だと思う」
「女性に約束をすっぽかされるのも悪くはないわね」
「やれやれ」
「クリ-ム」 R・F
「自分-40を過ぎて未だ曖昧模糊としているのだが-と言う人間を、漢字一文字で表せとその講師-トムとジェリ-のジェリ-が肥え年老いたような顔の-が言った。私の勤めるしがないハウスメ-カ-の研修であった。
私は迷わず「和」と答えた。そしてなぜその文字を選んだのか彼に語った。
「常に周囲との輪を重んじ、人を不愉快にさせないように気を配っています。仕事はゴール、目標を同じとする人たちが揉めたりすることは本来ありえない事ですから」等々。
人から嫌われたり不愉快な気持ちにさせることなど(ほとんど)無いと信じていた私を、この「クリーム」と言う話は恐怖に陥れ、同時に希望も与えてくれた。やれやれ。
「ウィズ・ザ・ビ-トルズ」 M・H
私がこの本を読んだのは夏の終わりの頃だった。
それは私にとっては他のたくさんの小説の中の一つにすぎず、あるいはそうではないかもしれない。その中で私は記憶が途切れる青年と出会った。
彼が言うには何時間、もしくは何日もの間記憶が突然抜け落ちてしまう事があると言う。
今から18年前の事だ。
彼の病気が治った事と妹と主人公の別れに因果関係を感じずにはいられなかった。
品川猿の告白 T.K
「僕は本当は人間よりも猿に近いのかもしれないと思う」
「それは人間は猿から進化したから、私たちはみんな半分は猿なんだという話?」
「いや、そうではなくて僕一人だけが猿なんだ。村上春樹の『品川猿の告白』という短編があるんだけど、知ってる?」
「『品川猿』なら聞いたことあるけど…」
「新しく出た短編集に収録されている続編だよ。『品川猿』に登場した猿のその後を描いていて、彼の苦悩が語られている。人の言葉を話す猿としての苦悩がね」
「それがあなたが猿の近似種である事とどう関係するわけ?」
「哀れな品川猿は中途半端に人間の言葉なんか覚えてしまったものだから、猿とも人間ともコミュニケーションが上手くとれずにつらい思いをしているんだ。僕は人生の半々をそれぞれ日本とアメリカで過ごしたから、彼の猿としての孤独はとてもよくわかる。同じ短編集に収録されている他の話の登場人物……つまり人間の登場人物のことだけど、僕は彼らよりも品川猿の方に共感できることに気が付いたんだよ」
「その場合、日本とアメリカはどちらが猿でどちらが人間なのかしら」
「それはちょっとわからないけど…」
「ふうん」
そう言って彼女はグラスを持ち上げ口元まで運ぶと、そこで手を止めて中のワインを少しの間眺めてから再びテーブルに置いた。彼女は三十分ほど前からこの動作を何度も繰り返していた。自分のグラスのワインは永遠に飲まれることがないという定理を証明するかのように。
「確かにあなたの言葉は時々わけがわからない。もしかすると本当に猿なのかもしれないわね。それに、あなたってすごく毛深いし」
「その通りだ」と僕は言った。
まったくその通りだ。
最後に課題本を撮影。

■開催後記
今回は棚を借りているブックマンションで読書会を行ったのですが、当然のことながら本に興味がある方が多いので、本屋で読書会を行う事の意味を感じました。
コロナは引き続き予断を許しませんが、人が集まるという面ではコロナ前と変わらなくなってきている印象です。ワクチンが開発されたらその後の反動がすごいでしょうね。
次回開催は11月を予定しています!今年中にあと2回出来ればいいなぁ。